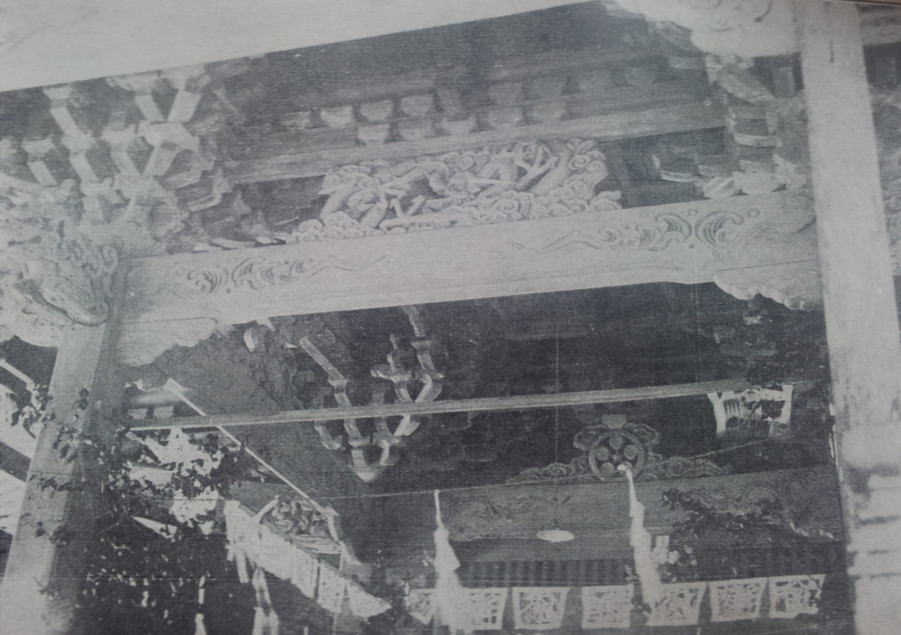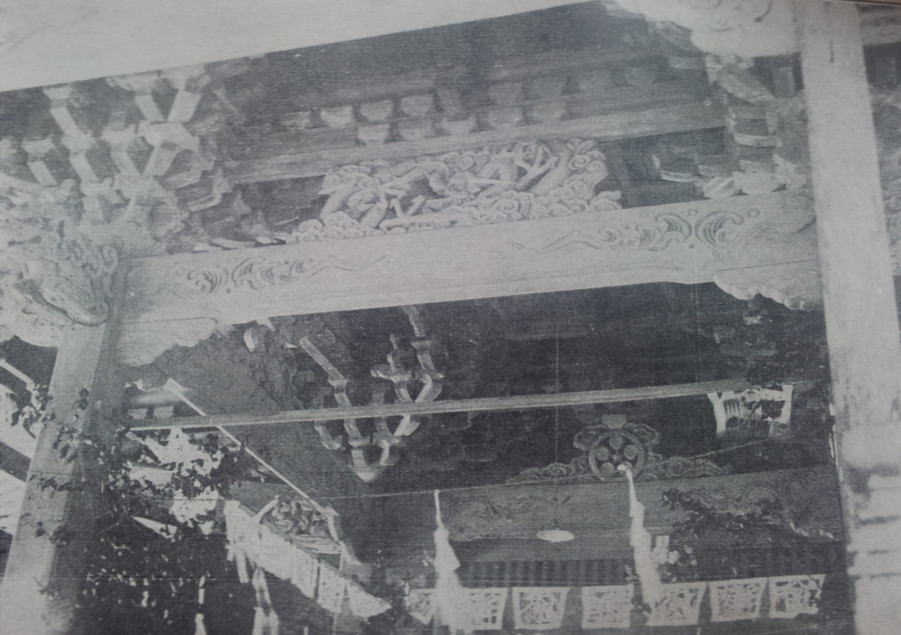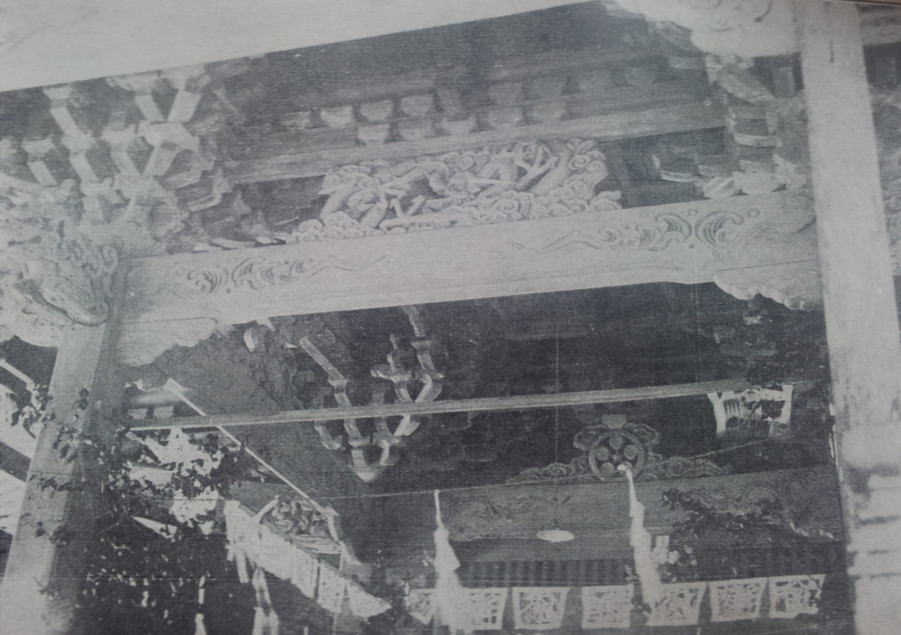池川町河島山神社本殿
トップページ>高知県の観光>高知県の美術>第三章武家美術時代>池川町河島山神社本殿
第三章武家美術時代
第二節建築
二、神社建築
本殿は用材は垂木を除き大部分櫸の良材を用いて建てられ入母屋造にて千鳥破風を南面せしめ桁行一間梁間四尺四寸にて棟の南面に幹唐破風をつけ屋根裏は繁垂木にて軒唐破風の懸魚は雲を刻しその下には桁の上に天女の透彫を用い本殿四面の桁の下には本枝輸を施し惻面に雲板がある、本殿四面の柱頭には斗拱があつて枠肘木を上下二重に重ね斗拱の間には蛙股を用いてある、本殿の四面には緣を繞らし櫚干を設け寶珠柱を建ててある、向拜の部分にてその柱はニ本となり虹梁の面に唐草を刻し柱頭の斗組は出組にて虹梁の拳鼻は象となりその表面には、頗る優れたる雀の透刻の蛙股があつて向拜の內上方は格天井となりその北方本殿の正面見付には寶珠に雲の蛙股がある、この建築は本殿に比して小に過ぎるけれども建築は堅國にして手法も劣ってゐない。