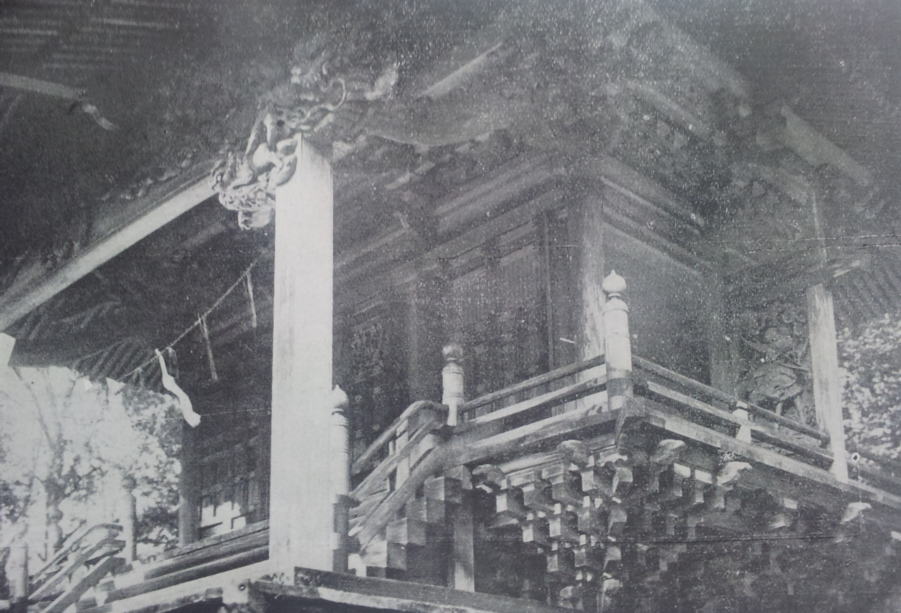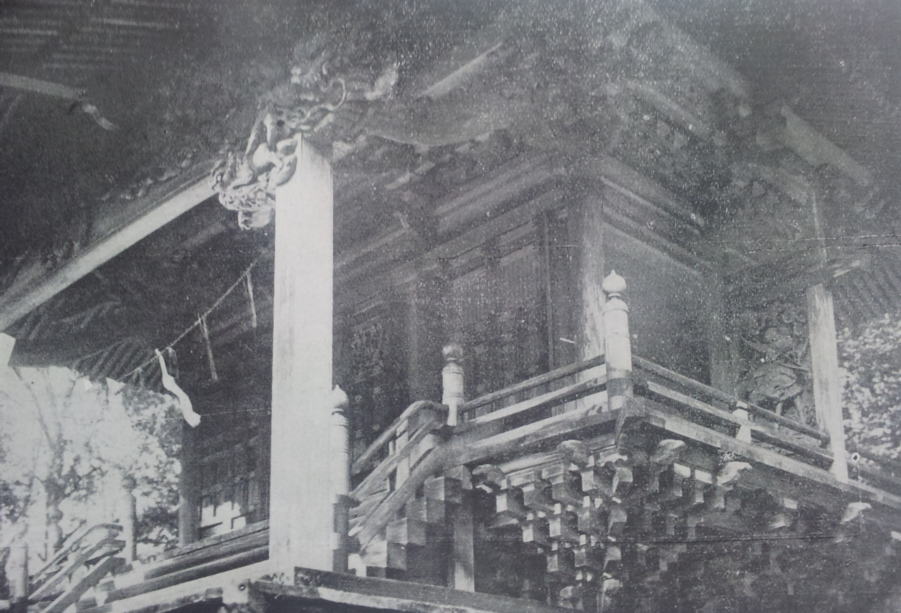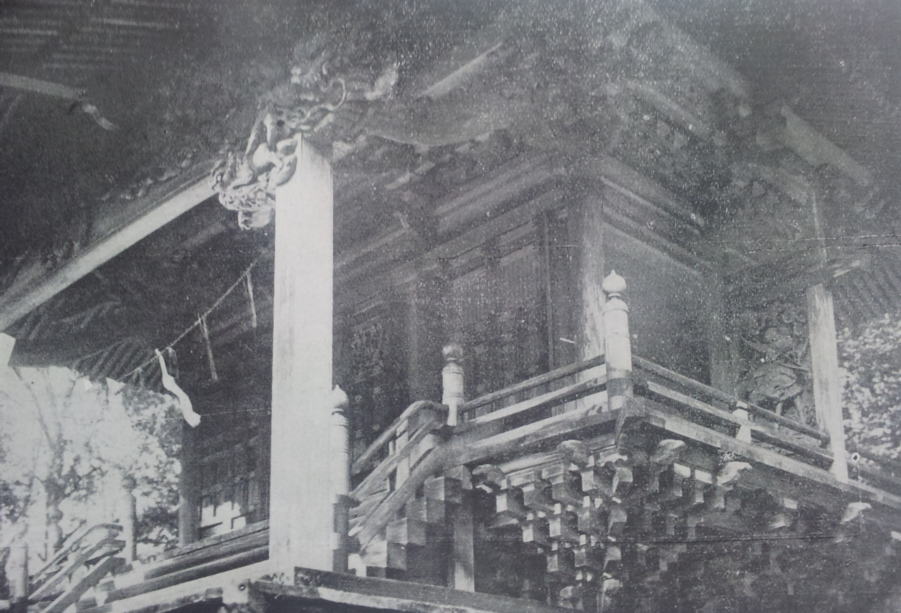德弘董齋
トップページ>高知県の観光>高知県の美術>第四章庶民美術時代>第三節繪畫と書道>日本畫と作家>德弘董齋
第四章庶民美術時代
第三節繪畫と書道
當代に於ける繪畫は從來の日本畫の外に洋畫勃興して空前の發達をなした、然して日本畫は南畫派北畫派、浮世繪派、四條派の數派に分れたるが當國にては南畫の勢カ最も大にして土陽美術展覽會
に出品せられたる日本畫の大多数は此の畫派であつてその代表的作家に山岡米華を出し日本的の盛 名を馳せてゐる。北畫は當代の初期に於て行はれ宮田洞雪、弘瀨竹友齋がこれをょくし浮世繪派は
山本昇雲が之を代表し四條派は柳本素石が之をよくしてゐる。洋畫はアカデミー派を國澤新九郡が 明治五年英國偷敦に留學してニヶ年間修業して歸朝し東京麴町區平川町に彰枝堂を開きて之を授け
クラシック派は石川寅治が上京して小山正太郞の不同社に學んで出藍の譽を擧げ印象派は山脇信德 が我國に於ける先鞭を附けその闘將として榮冠を獲得してゐる。かくして各流各々その據る所と守
を處を異にし研を競ひ技を凝して百花繚亂の有樣であつたが大正年間に入りては更に一般美術界の 大勢に從つて日本畫と洋畫と漸次接近し日本畫は院展風の作家出で洋畫には現代佛蘭西畫家の作風
の影響を受くること頗る多きを加ふるに到つた。次に日本畫及び洋畫の作家につき列傳的に紹介することとしやう。
一、日本畫と作家
明治初年前後にありて南畫家として名ありしものは橋本小霞、德弘董齋である
德弘董齋
德弘董齋は名益、字貞吉、通稱は祥吉又孝藏といひ石埭の別號がある。高知城西中須賀の人にて父石門もと砲術の家筋なりしも餘業を以て畫を善くした、董齋又其の跡を繼ぎ生れながら丹靑を好み家業を喜ばす壯年の頃砲術修業として江戶に登りしに廣瀨台山光明寺雲室等の門に出入し南宗畫を學び大に得る處あり、歸國後自ら家業を廢して繪畫を以て專ら一家の門戶を開く、書を乞ふもの頗る多かりき、董齋の畫筆致輕婉にして洒脫の氣味あり、山水尤妙である、世に橋本小霞と並稱し明治初年土佐南畫のニ名家とせられてゐる。彼の勤王家武市瑞山は嘗て其の門下に遊び南畫を學びしことがあつた明治十四年五月廿五日歿し享年六十餘歲であつた、その遺作は時代新しき爲め各地に存するも八百屋町川崎源右衛門氏方にある蓮に白鷺の畫は絹本尺八にて長さ四尺五分あり董齋の代表作である。