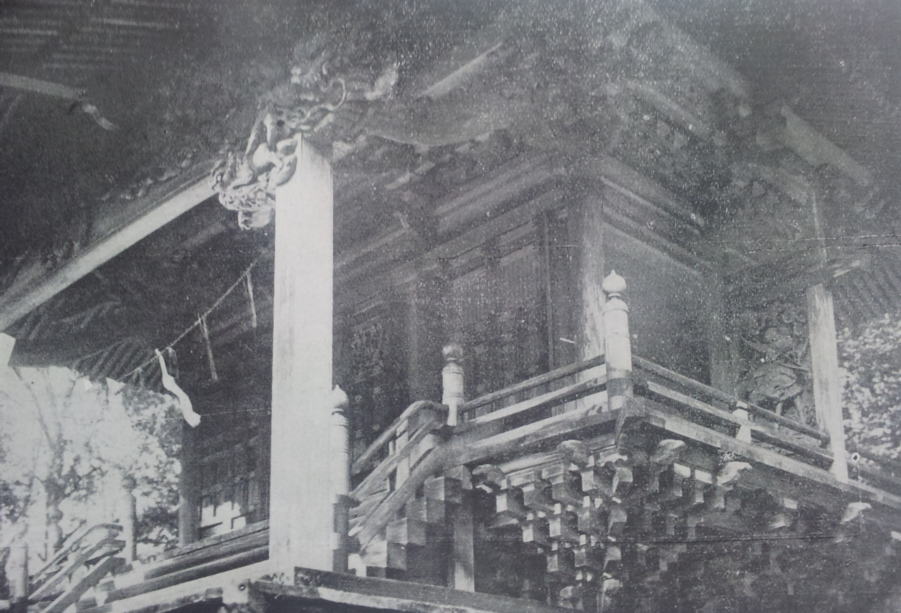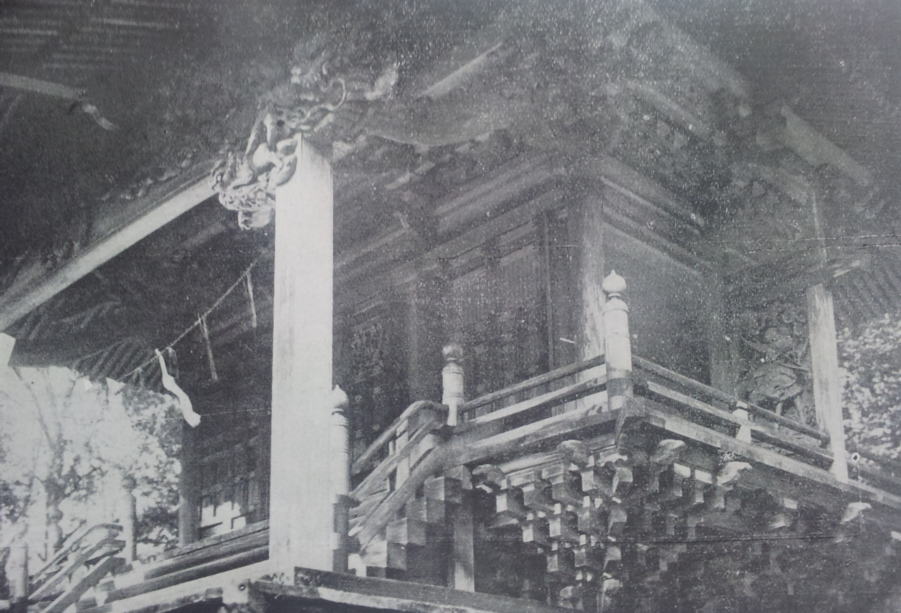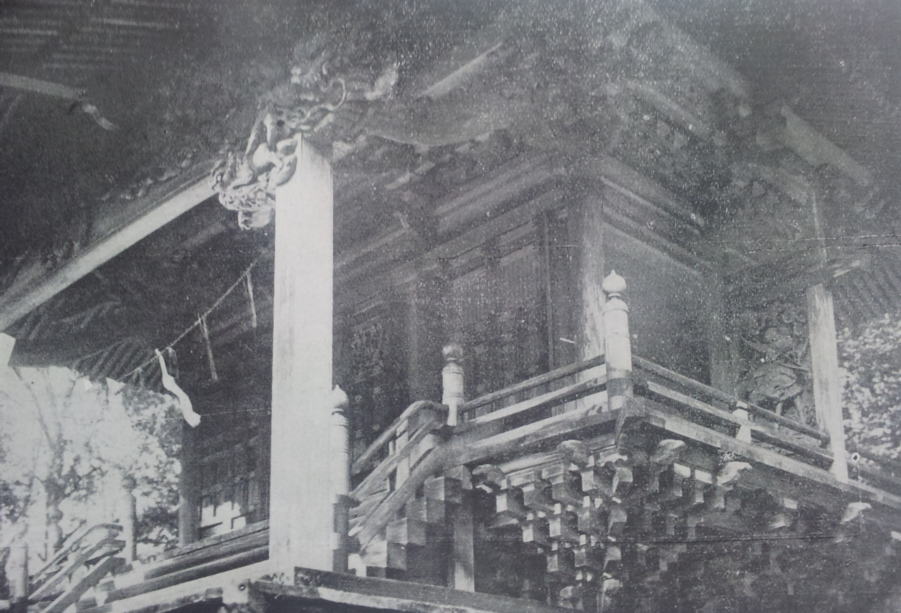川谷尙亭
トップページ>高知県の観光>高知県の美術>第四章庶民美術時代>第三節繪畫と書道>書道>川谷尙亭
第四章庶民美術時代
第三節繪畫と書道
當代に於ける繪畫は從來の日本畫の外に洋畫勃興して空前の發達をなした、然して日本畫は南畫派北畫派、浮世繪派、四條派の數派に分れたるが當國にては南畫の勢カ最も大にして土陽美術展覽會
に出品せられたる日本畫の大多数は此の畫派であつてその代表的作家に山岡米華を出し日本的の盛 名を馳せてゐる。北畫は當代の初期に於て行はれ宮田洞雪、弘瀨竹友齋がこれをょくし浮世繪派は
山本昇雲が之を代表し四條派は柳本素石が之をよくしてゐる。洋畫はアカデミー派を國澤新九郡が 明治五年英國偷敦に留學してニヶ年間修業して歸朝し東京麴町區平川町に彰枝堂を開きて之を授け
クラシック派は石川寅治が上京して小山正太郞の不同社に學んで出藍の譽を擧げ印象派は山脇信德 が我國に於ける先鞭を附けその闘將として榮冠を獲得してゐる。かくして各流各々その據る所と守
を處を異にし研を競ひ技を凝して百花繚亂の有樣であつたが大正年間に入りては更に一般美術界の 大勢に從つて日本畫と洋畫と漸次接近し日本畫は院展風の作家出で洋畫には現代佛蘭西畫家の作風
の影響を受くること頗る多きを加ふるに到つた。次に日本畫及び洋畫の作家につき列傳的に紹介することとしやう。
三、書道
明治及び大正時代に入り書道は一般に衰追せず當代の初にありては前代の趨勢を繼承して作家尠しとせず、明治の初めにありては維新の元動にて書に巧なるものを細川潤次郞、田中光顯とし學者の能書家としては岩崎秋冥あり光顯は張三州につき更に古今の書を研究し一家をなす濱ロ秋水、三浦ー竿、西森鐵研、田中璞堂、淺川石颿、西川菱花等のあるあり。大正昭和時代に入り川谷尙亭、益田石華等も出でてゐる。
川谷尙亭
川谷尙亭は明治十九年を以て安藝郡川北村に生る。高知縣立安藝中學校を明治卅八年頃に優等にて卒業して支那上海なる東海文書院に入學せしも病氣にて退學し後東都に出で日下部鳴鶴につき書道を研究しその高弟として盛名あり蕾に師の書風を學ぶのみならず晋唐の書道を研讚し一家をなしてゐる。大正年間となり大坂市東區味原町に住し多數の門人を指導する側に書の研究及び書道講習錄を發行し全國に數万の會員を有す現代日本知名の大家であつて著述多く楷書楷梯其他愛讀せらる目下日本書道史編纂中にて前途有望の書家である。