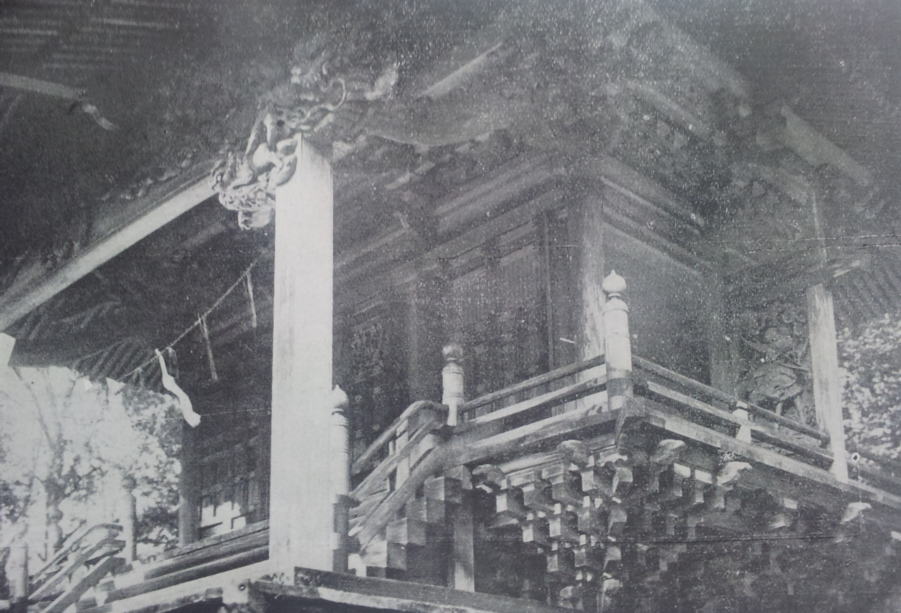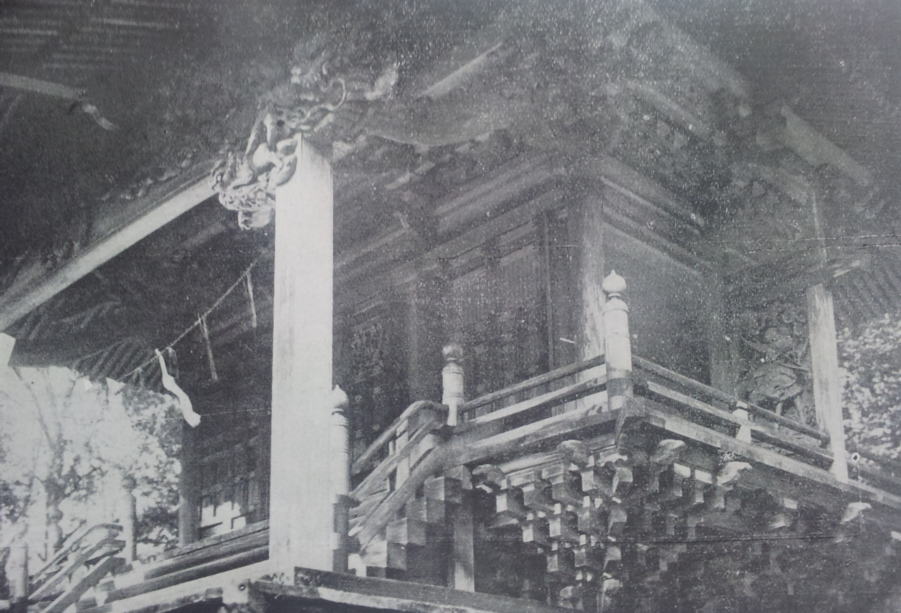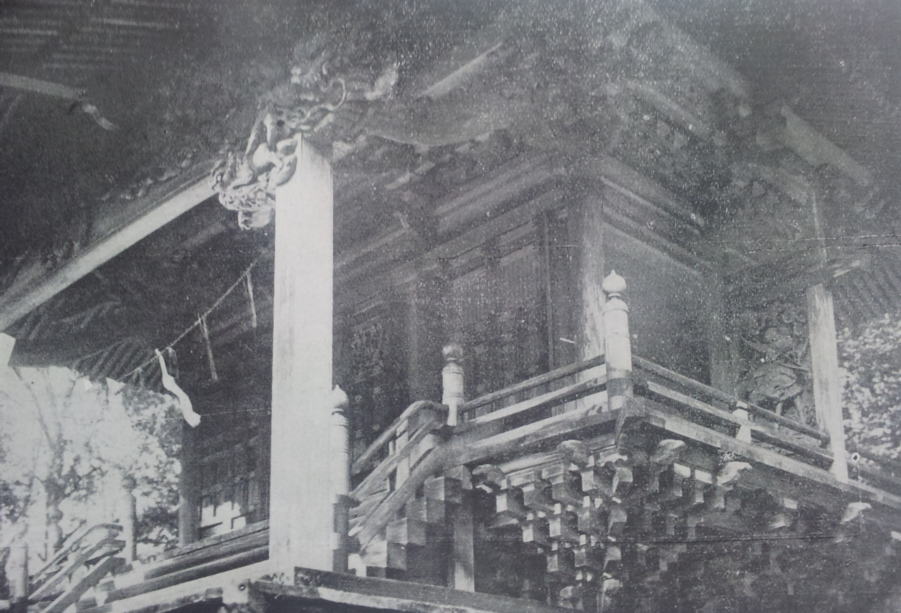神矢敎親
トップページ>高知県の観光>高知県の美術>第四章庶民美術時代>神矢敎親
第四章庶民美術時代
第五節美術工芸
當代に於ける美術エ藝は歐洲文化の影響を受けて古美術地を拂ひ刀劍、銅鏡、鳄等は又見るベからず尾戶燒も僅に製作せらるるのみにて往古の名殘を止むるに過ぎず漣田豐水によりて創始せられたる古代塗も門人小栗正氣その後を繼承せしも後進繼かず漸次品質の低下なり美術としての價値を失ふに到つた。明治四十ニ年の頃に高知市會議員信淸權馬の獨カにより土佐の美術工藝の振興を期し蒔繪及漆川を主とする敎習所を開設せしを明治末年より大正初年に渉り高知市立工業學校として生徒を收容せしが卒業生就職難により大正五六年頃閉鎖した、斯の如き內にありて美術エ藝家として名あるものを神矢敎親、吉田源十郎、鈴木素興となす
神矢敎親
神矢敎親は幡多郡奥內村に明治十八年七月を以て生る。明治三十九年三月高知縣師範學校を卒業し仝四十五年三月東京美術學校金工科を卒業し直に同校に奉職し生徒を指導し益々彫金術並にエ藝化
學を研究し大正七年第六回農商務省エ藝展覽會に出品して三等賞を受く其の後文部省より欧州留學を命ぜられ彼國に遊學して歸朝し東京高等エ藝學校の創設せらるるや仝校敎授に補せられ現今に致
つてゐる